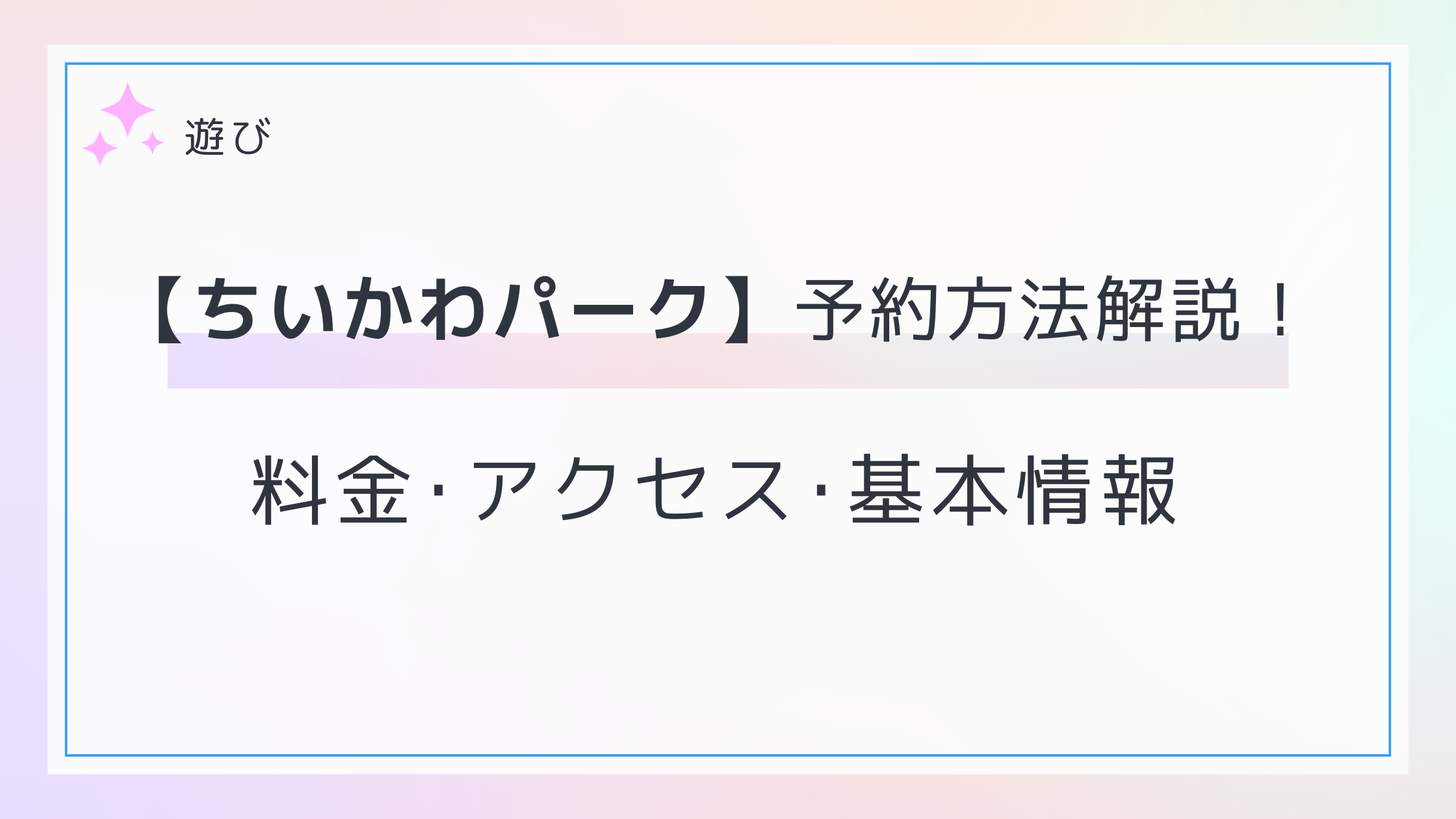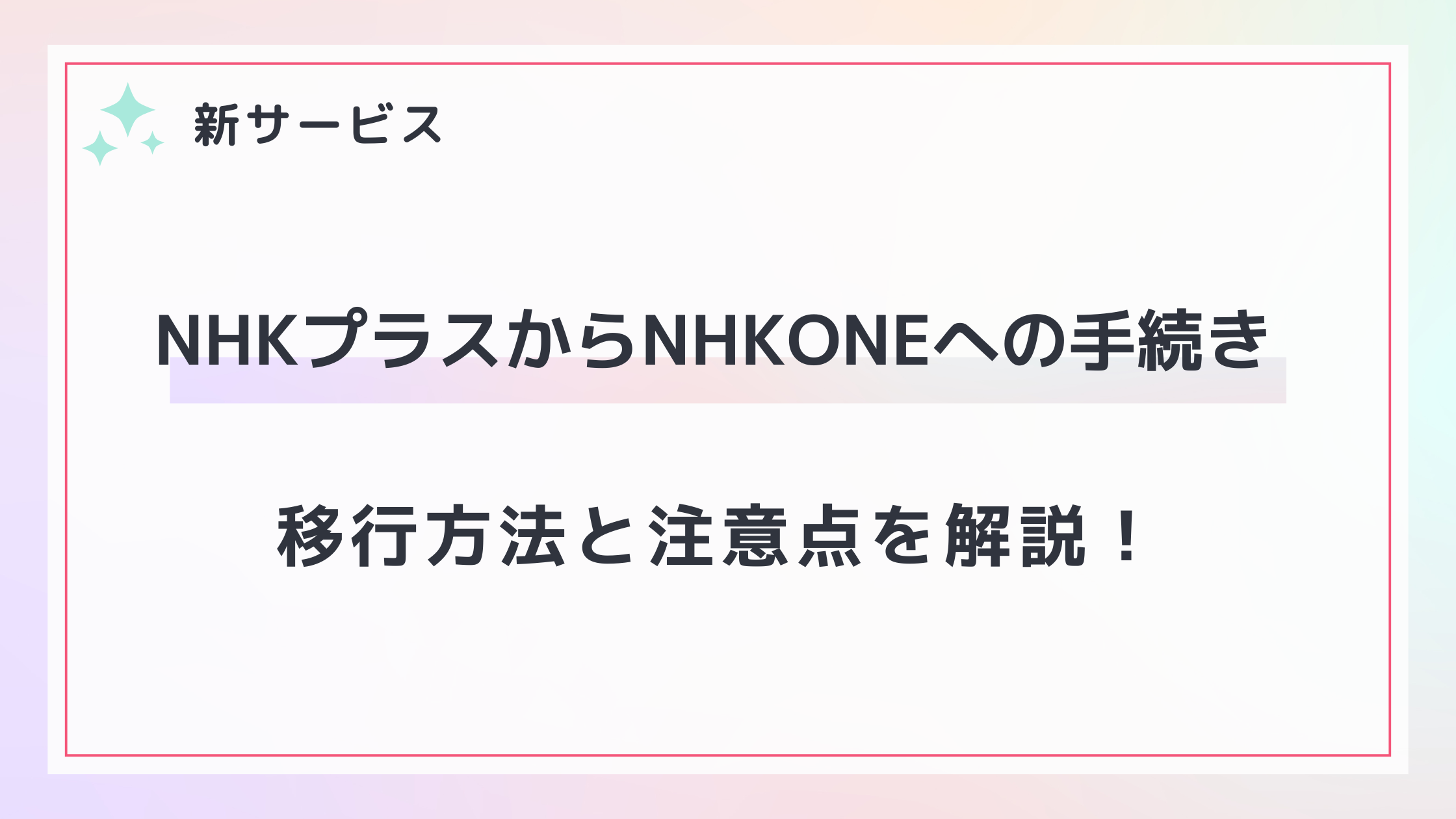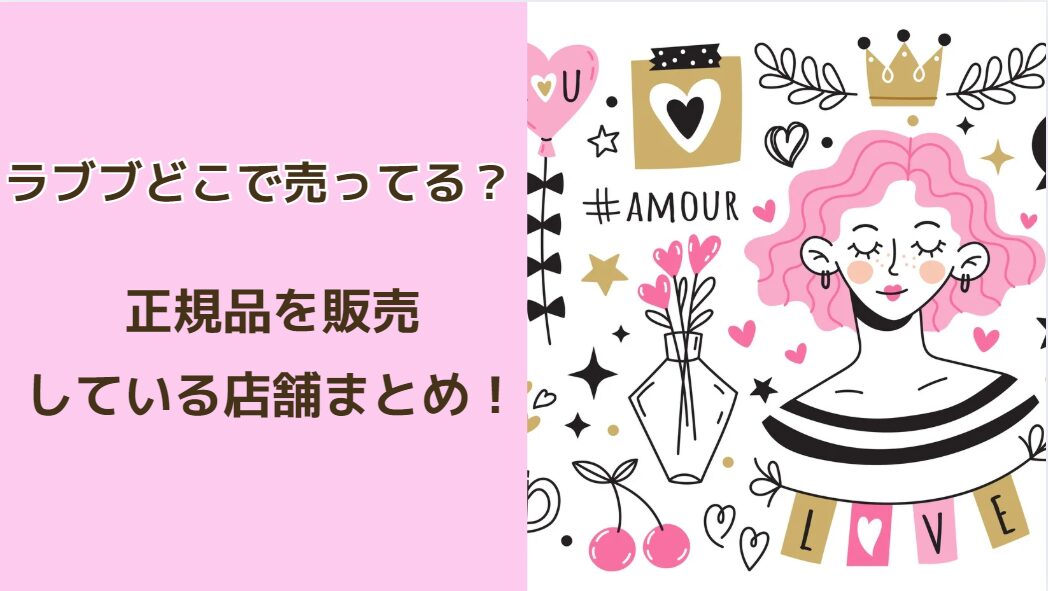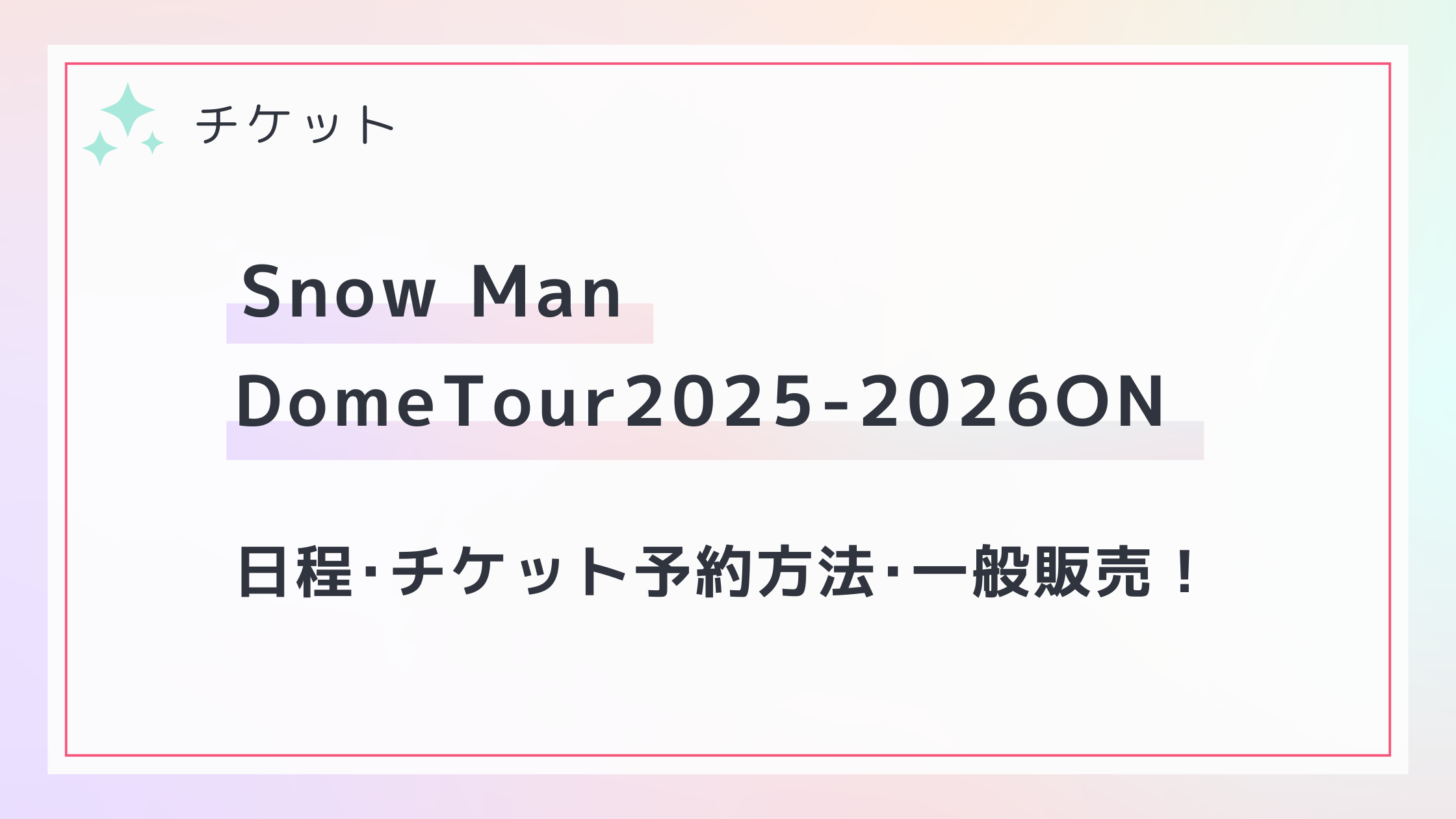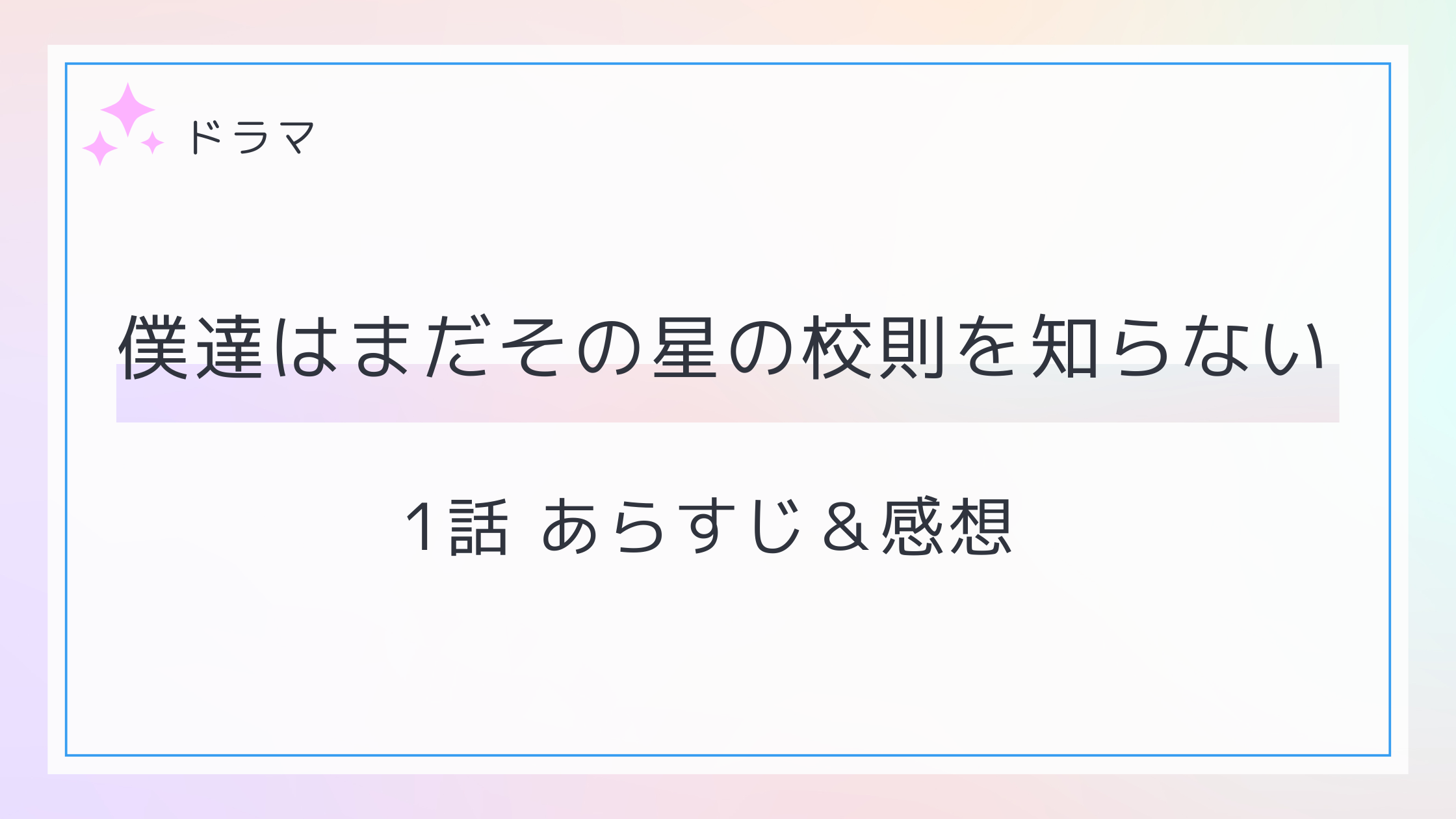月曜夜に放送が始まったフジテレビの新ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」。
当記事では、1話のあらすじ&感想をまとめました。
「僕達はまだその星の校則を知らない」1話では、スクールロイヤー・白鳥健治が高校に派遣され、校則と向き合いながら若者たちの葛藤に寄り添う姿が描かれます。
制服問題、不登校、生徒自身が校則を問い直す模擬裁判といったテーマが、現代の教育やジェンダーの在り方に深く切り込む第1話でした。
「僕達はまだその星の校則を知らない」1話のあらすじ・感想を中心に、注目ポイントを読み解きます。
僕達はまだその星の校則を知らない1話のあらすじ
物語の中心となるのは、臆病ながらも誠実なスクールロイヤー白鳥健治(磯村勇斗)。
彼の高校派遣によって、閉ざされていた生徒たちの心に変化が訪れ始めます。
裁判を通して校則に向き合いながら、生徒たちが抱える葛藤や希望が浮き彫りになる構成でした。
スクールロイヤー・白鳥健治の高校派遣
物語は白鳥健治が高校へ派遣されるところから始まります。
弁護士でありながら教育現場に不慣れな彼は、当初周囲から距離を置かれるが、持ち前の誠実さと相手に寄り添う姿勢によって、生徒たちとの信頼関係を少しずつ築いていきます。
彼の派遣は単なる法的サポートに留まらず、校則や教育そのものを見つめ直すきっかけとなっていきます。
スクールロイヤーという立場が、既存の教師や生徒と異なる視点で描かれます。
その静かな存在感が、生徒たちの閉ざされた心を動かしていく展開に繋がっていくのか。
制服問題と模擬裁判の提案
校内で問題となっていたのが「制服は性別に応じて着用しなければならない」という校則。
これに違和感を覚えた生徒たちの声に、健治は耳を傾けます。
学校のルールをただ守るのではなく、自分たちで考え直すための場として、模擬裁判を提案する姿が印象的でした。
生徒たちが「自分たちの学校を変える力がある」と感じるきっかけとなり、校則の在り方を問い直す空気が生まれます。
裁判の準備を進める中で、生徒同士の対話や問題意識が深まっていきます。
生徒会長と副会長の不登校の背景
生徒会長の蒼井と副会長の加賀谷が不登校であることを知った白鳥。
その背景には、校則による自己否定や周囲との摩擦があり、個性を抑え込まれた経験が強く影響しているようです。
規則に従うことが正しいこと、とする空気に疑問がなげかけられます。
模擬裁判の開催を機に、学校という場所が再び自分の声を発する場になり得ることに気づく生徒たち。
理事長・尾碕美佐雄の説得と裁判の結末
事長の尾碕は、伝統や秩序を重んじる厳格な人物として登場します。
校則は守るべきものという考えが強く、生徒たちの声には耳を貸さない姿勢を貫く。
しかし、模擬裁判での生徒たちの本気の訴えに、次第に態度を変えていく様子も描かれました。
模擬裁判の後行われたアンケートで、制服はあった方が良いとする意見が大多数という結果に。
健治の過去と学校への向き合い方
健治自身も過去に教育の現場で何か傷ついた経験を持っている様子。
そのため当初は学校という場に対して距離を置いていたが、生徒たちとの関わりを通じて、その見方に変化が表れ始めます。
模擬裁判で生徒の言葉に耳を傾け、彼らの成長を見守る中で、自分自身が何を恐れていたのか、そして本当に向き合うべきものは何なのかに気づき始める。
健治の変化は、物語全体を通して静かに響くテーマの核となっていくのでしょう。
僕達はまだその星の校則を知らない1話の感想
第1話では、従来の学園ドラマでは扱われることの少なかったテーマが描かれました。
登場人物たちの感情の揺れや対話の温度感を感じました。
俳優陣は、各キャラクターの内面が自然と伝わってくる場面が多いです。
今までにない学園ドラマ
このドラマの注目すべきポイントは、ただの青春群像では終わらないところ。
校則をめぐる議論を通じて、学校とは何か、個性とは何かというテーマが浮かび上がり、ドラマながら社会的な問題提起もなされています。
過度な演出はなく、対話と葛藤で物語が進むスタイルです。
一般的な学園ものにありがちな恋愛・友情だけでなく、法や制度など通して若者たちの内面が映し出していく点が、今までにない感じました。
初回ながら印象的な構成と展開で今後の展開も楽しみです。
磯村勇斗の演技とキャラクターの魅力
スクールロイヤー・白鳥健治を演じる磯村勇斗さんの繊細な演技が印象的でした。
一見控えめな態度の中に、芯の強さや過去への苦悩が滲み、視線や動きで表現。
感情を爆発させるタイプではなく、沈黙の中に込められた思いがあるような。。
その余白を感じさせる演技が、白鳥というキャラクターに説得力を与えていると感じました。
宮沢賢治の詩的要素と世界観の融合
ドラマには、宮沢賢治の詩や思想を連想させる表現が散りばめられてています。
天文台や星といった象徴が、見えないものを見ようとする姿勢の象徴でもあるのかもしれません。
ドラマには文学的な香りが漂っていて、なんだか余韻が残る構成です。